考えましょう「住まいの終活」
人生の最期を考えたとき、「遺された家族に負担はかけられない」と考える方は多いと思います。
そして、ご自身が亡くなられた後の「住まい」に目を向けると、ご家族が住まわれるのか、誰も住まずに空き家になるのか、空き家になった後の管理は・・・。
家族とともに大切な時間を過ごしたお住まいが、管理されずに空き家として放置され、将来、地域やご近所へ迷惑をかける状態になることは、望む未来ではないはずです。
しかし、大切なお住まいの今後の取扱いをしっかり決めておかないと、トラブルが起きたときに、遺されたご家族へ、もうあなたの思いを伝えることはできません。
遺されたご家族とお住まいの今後のためにも、「住まいの終活」を考えてみませんか?
相続登記の義務化
登記簿を見ても所有者が不明である「所有者不明土地」の増加という社会問題に対処するため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
●不動産を相続した相続人は、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法務局への相続登記の申請を義務付け。
※この義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
空き家になると・・・
人が住まなくなった建物は劣化が進み、外壁などのはく離、屋根の軒折れ、草木の繁茂、害虫の発生、動物の住みつきにつながります。
さらに管理が放置され続けることで倒壊する危険性が高まるなど、放置された空き家が周囲に被害を与えてしまうと、相続人などへ損害賠償責任を負わされる可能性もあります。
始めましょう「住まいの終活」
活用しましょう「住まいのエンディングノート」
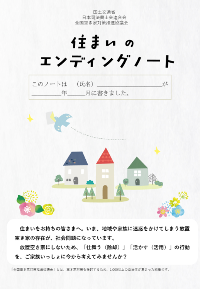
国土交通省、日本司法書士会連合会、全国空き家対策推進協議会が協力し、「住まいのエンディングノート」を作成しています。
このノートには、家系図や建物(土地)の所有の状況に加え、これらを今後どうしたらよいかなどの情報が記入できます。
今後のご家族への負担を減らすためにも、大切な「住まい」に重点を置いたエンディングノートを、ぜひご活用ください。
放置空き家にしないために、「仕舞う(除却)」「活かす(活用)」の行動を!
ご家族で話し合いましょう
お住まいの将来のあり方を、ご家族でしっかり話し合いましょう。
相続で無用なトラブルを避けるためにも、遺言書の作成も有効です。
※遺言書の参考は「エンディングノート(法務省/日本司法書士連合会)(PDFファイル:7.6MB)」
家財の片付けは計画的に
故人の思い入れのある家財を処分することは、誰でも戸惑うものです。
しかし、お住まいを利活用(売買・賃貸)するにあたり、家財が多いと契約交渉が難航する場合があります。
計画的な家財の片付けも、スムーズな住まいの利活用につながります。








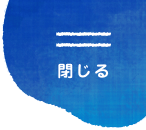


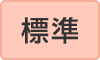


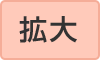



更新日:2025年08月01日