南会津町景観重要建造物・樹木の指定
景観重要建造物及び景観重要樹木の指定とは
景観重要建造物や景観重要樹木は、景観法(平成16年法律第110号)第19条及び第28条の規定に基づき、地域の自然、歴史、文化などから見て、建造物の外観や樹木の姿が景観上の特徴を有し、地域の景観づくりを進めるうえで特に重要と認められるものを所有者などの同意を得たうえ、景観行政団体の長(町長)が指定を行う制度です。
町では地域の景観づくりのシンボルとなる景観重要建造物・樹木として指定するとともに、所有者等に支援を行いながら、景観の意識向上や地域の特性を活かした景観づくりを進める重要な核となる建造物や樹木の保全、活用を図っていきます
南会津景観計画に定める指定方針
- 道路などの公共の場所から容易に見ることができるもの
- 地域のシンボル的な存在であり、地域の景観を特徴づけ良好な景観形成に寄与しているもの
- 所有者もしくは管理者に保全または活用の意思があること
- 地域に親しまれ、愛されていること
指定対象を検討する建造物・樹木
- 地域の景観に影響の高い建造物・樹木
- 町又は県の指定重要文化財等の建造物
- 町並みや集落景観と一体となった並木、樹林
- 河川堤の並木等、優れた自然景観を形成する樹林
- 地域の歴史・文化を継承し、地域の景観の特徴をなす建造物
- 国登録有形文化財等歴史・文化性のある建造物
- 用水を取り入れた住まい、曲家、蔵等地域に継承される材料や形式の建造物
- 寺の樹木、鎮守の森等歴史性・文化性のある樹林
- 地域のランドマークとなる建造物
- 優れたデザインを有し、周辺地域の良好な景観を特徴づけている建造物
- 駅舎等、交流の場となり親しまれている建造物
- 町、県指定天然記念物等の樹木
- 見通せる場所にある巨木
- 維持管理を行う個人又は団体がある建造物
南会津町の景観重要建造物・樹木
景建第1号・景樹第1号


木造で建てられた旧中荒井分校の写真 拡大画像 (JPEG: 8.1KB)
赤色の木造づくりの建物の横には子安地蔵堂が建ち、周辺にしだれ桜などの木が立っている写真 拡大画像 (JPEG: 12.0KB)
|
指定番号・名称 |
|
|---|---|
|
指定年月日 |
平成28年3月1日 |
|
所在地 |
南会津町中荒井字桑木原1088番地 |
地区の中心に位置し、大正15年に建設され、本町では唯一現存する木造校舎であり、地域の教育施設として親しまれてきた歴史的な建造物である。周辺には教育の地に記念となるべき樹木として植樹をした百年桜や子安地蔵堂があり、一体的な歴史的風致を形成している。地域の中心的な憩いの場所になっており、地区のシンボルとして良好な景観形成に重要な役割を果たしている。
景建第2号


茅葺の小屋が建ち、後方には美しい紅葉の木々が立っている写真 拡大画像 (JPEG: 10.0KB)
広い田んぼが広がり、後方には青々とした木々と茅葺の小屋が建っている写真 (JPEG: 7.4KB)
|
指定番号・名称 |
景建第2号 森戸の雨屋 |
|---|---|
|
指定年月日 |
平成28年3月1日 |
|
所在地 |
南会津町森戸156番地1 |
雨屋は、明治初期に建設された木造茅葺き屋根の簡素な建物で、屋敷から離れた場所に建っており、雨天の際の作業小屋として使われていた。
周囲は南側の佐倉山や西側の立岩山を背景にして、一面が田園風景の中、茅葺の小屋が建ち、周辺の景観との一体感やタイムスリップしたような空間となっており、地区のシンボルとして良好な景観形成に重要な役割を果たしている。
景樹第2号


神社境内の前に赤い小さな鳥居があり、大きなモミの木が立っている写真 拡大画像 (JPEG: 12.4KB)
木造づくりの建物の周りに大きなモミの木が立っている写真 拡大画像 (JPEG: 9.5KB)
|
指定番号・名称 |
景樹第2号 稲荷様の大モミの木 |
|---|---|
|
指定年月日 |
平成28年3月1日 |
|
所在地 |
南会津町中荒井字久宝居732番地1 |
樹高については、約20メートル、幹回り6.1メートル、幾多の落雷により、頂部を失っているにもかかわらず、クリスマスツリーのような格好になって、枯れることなく地域の安寧を見守ってきている巨木である。
地区の中心に位置し、稲荷神社境内にあることから地区の中心的な憩いの場所になっており、地区のシンボルとして良好な景観形成に重要な役割を果たしている。
景樹第3号


石段の上に三角屋根の建物が建ち、建物の間に大きな1本の木が立っている写真 拡大画像 (JPEG: 9.5KB)
道路脇に古民家が立ち並び、青々とした大きな木が立っている写真 拡大画像 (JPEG: 11.1KB)
|
指定番号・名称 |
景樹第3号 弘法の湯のコウヤマキ |
|---|---|
|
指定年月日 |
平成28年3月1日 |
|
所在地 |
南会津町湯ノ花321番地 |
地区の中心に位置し、樹齢120年といわれ、根回り約3メートル、高さ約15メートル、明治33年田代山開山者大山善八郎時澄が和歌山県高野山より持ち帰り植栽したと伝えられている。
地区には4つの共同浴場、古民家を利用した旅館・民宿も多く、旧舘岩村から景観に配慮した町並みづくりを進めており、風情が息づいている地区である。地区の歴史的な背景からも地区のシンボルとして良好な景観形成に重要な役割を果たしている。








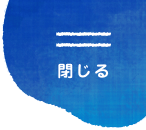


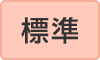


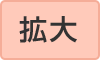



更新日:2021年04月01日