会津田島祇園祭の歴史



歴史
会津田島祇園祭は、鎌倉時代の文治年間(1185年頃)、時の領主長沼宗政の祇園信仰により、この地に祇園の神(牛頭天王須佐之男命)を居城鎮護の神としてまつり、祇園祭の制を定め、旧来よりの田島鎮守の田出宇賀神社の祭りと共に行われた事が起源とされています。この祭りは古くより『西の祇園社、中の津島社、東の田出宇賀社』と言われ日本三大祇園祭の一つと称し伝えられています。
明治12年より田出宇賀神社の祇園祭日に併せ、隣地にまつる熊野神社祭礼を祇園祭の格例に準じて行うことが定められました。
祭りの賄い献立にふきを多く使用することから、俗に「富貴祭=ふきまつり」とも呼ばれています。また御神酒に濁酒を使用することから「どぶろく祭り」、屋台の運行が激しいことから「けんか祭り」とも呼ばれます。
お党屋制度(国指定重要無形民俗文化財)
会津田島祇園祭は、お党屋制度とよばれる現在9組の当番お党屋組が、1年間党本の家を支えて祭事を担当する制度によって運営されています。当番お党屋組を中心に、去年のお党屋組「渡し」と、来年のお党屋組の「請取り」3組が織り成す祇園祭は1年がかりの大行事です。この820余年の伝統が、昭和56年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。








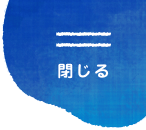


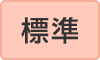


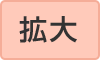



更新日:2021年06月17日