後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方と65歳から74歳までの一定の障がいがある方で、申請により広域連合に認められた方が加入する医療保険制度で、加入者の皆さん、現役世代(若い世代)、国や自治体等がお金を出し合い、病気やケガの治療にかかる医療費の負担を少なくする助け合いの仕組みです。
特に、医療機関での診療には現役世代よりも軽い1割の窓口負担(現役並みに所得がある方は3割)で医療を受けられます。また、医療機関に支払う1ヶ月あたりの自己負担限度額も現役世代より低く設定された制度で、平成20年4月から始まりました。
運営主体は、福島県内の市町村が加入する「福島県後期高齢者医療広域連合」で、県内の市町村と協力して次のような業務を行います。
福島県広域連合と市町村の事務分担
福島県広域連合
運営主体となり、
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付に関する決定
- 保険証の交付
などを行います。
市町村
- 保険料の徴収
- 申請や届け出の受付
- 保険証の引渡し
- 保険証の再交付、返還の受付
などの窓口業務を行います。
医療給付費等の財源
後期高齢者の病気やケガの治療にかかる医療費は、公費(国や自治体の負担)で約5割、若年層の保険料(現役世代からの支援金)で約4割、後期高齢者の納める保険料で1割とそれぞれ一定割合の負担により支払われます。
皆さんが納めた保険料は医療機関等へ支払われる医療費の大切な財源となり、制度を運営しています。

後期高齢者医療制度担当窓口
本庁住民生活課国保年金係 0241-62-6120
舘岩総合支所町民課住民係 0241-78-3325
伊南総合支所町民課住民係 0241-76-7712
南郷総合支所町民課住民係 0241-72-2225
対象者と保険証について
後期高齢者医療制度では、保険証(被保険者証)が一人に一枚交付されます。
加入する前に使用していた保険証は、加入していた保険者(国民健康保険・被用者保険《健康保険組合・組合健保等》)に返却してください。
対象者について
75歳以上の方
75歳になる誕生日の前月下旬頃に保険証を郵送します。特に加入の手続きはありません。
県外からの転入の方は、転入の手続き後、「負担区分等証明書」と印かんを持って後期高齢者医療担当窓口にお越しください。保険証は後日、郵送します。
一定の障がいをお持ちの65歳から74歳の方(注釈)
一定の障がいをお持ちの65歳から74歳の方は、申請していただいき、広域連合に認められた時に後期高齢者医療制度の加入者となります。
申請日以降の任意の日からの加入となり、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険等の「脱会(届)」が必要となります。
(注釈)65歳から74歳で次に該当する方
- 障害者手帳(1級から3級、4級の下肢障がい、4級の音声障がい・言語機能又はそしゃく機能障がい)
- 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)
- 療育手帳 A(重度、最重度)
- 障害年金(1級、2級)の方は年金証書
後期高齢者医療担当窓口にて上記の証明等を確認のうえ、保険証が交付されます。
なお、一定の障がいの状況を確認できない方については、個別に広域連合に照会となります。
申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 身体障害者手帳、障害年金証書等(障がいの状態がわかる証明書)
(注意)前加入の保険で「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、申請時にお持ちください。後期高齢者医療制度でも「特定疾病療養受療証」の申請が別途必要となります。
保険証について
保険証は後期高齢者医療保険の加入者であることを証明し、有効期限は直近の7月31日までとなります。
世帯の所得状況に応じて医療機関窓口での負担割合が1割または3割へ変動するため、毎年8月1日に更新いたします。新しい保険証は7月下旬に発送いたします。
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険は加入者の皆さんや現役世代、国や自治体等が一定の割合でお金を出し合い、病気やケガの治療にかかる医療費の負担を少なくする助け合いの仕組みです。そのため、被保険者の皆さんにはその負担能力に応じて公平に保険料をご負担いただくことになります。
保険料の算定方法
保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計となり、個人ごとに算定されます。

所得が少ない方の保険料の軽減について
所得が少ない世帯の被保険者については、下記のとおり保険料の軽減が受けられます。
被保険者以外が世帯主の場合、世帯主の所得により軽減が受けられないことがあります。
1 均等割の軽減(世帯の世帯主及び被保険者数の合計所得金額による)
| 総所得金額が下記の基準を超えない世帯 | 減額割合 |
|---|---|
|
基礎控除額(33万円) |
8.5割 |
|
8.5割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険者全員が、年収80万円以下(その他の所得がない) |
9割 |
|
基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く) |
5割 |
|
基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数 |
2割 |
(注意)所得とは、すべての収入から必要経費等を引いたもの(年金・給与収入の場合は計算式があります)から、退職所得を除き、基礎控除33万円を引いたものをいいます
(注意)世帯構成員中に所得の申告がすんでいない方がいるときには、軽減が受けられない場合があります。
2 所得割額の軽減
所得割額を負担する方のうち、所得金額が58万円以下の方は、 所得割額が5割軽減されます。
(年金収入のみの場合、153万円超211万円以下の方)
|
総所得金額が下記の基準を超えない世帯 |
減額割合 |
|---|---|
|
前年の所得 - 基礎控除額(33万円) = 58万円以下 |
5割 |
3 被用者保険(市町村国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません。)の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日において、被用者保険(市町村国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません。)の被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、負担軽減のため所得割額は賦課されず、均等割額が9割軽減されます。
保険料の減免について
被保険者ご本人や世帯主の方が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど特別な事情により、預貯金などの資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、役場後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。保険料の減免や徴収の猶予ができる場合があります。
後期高齢者医療保険料を納めないでいると
災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続け、納付相談にも応じない方は、下記のとおりになります。
- 「短期被保険者証」の交付
有効期限が短い短期被保険者証を交付します。 - 保険給付の制限
特別な事情もなく、保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止める場合があります。
医療機関で支払う費用(一部負担金など)は
「保険証」を医療機関の窓口で提示していただき、外来・入院ともかかった費用について現役世代よりも軽い1割(現役並みに所得がある方は3割)を負担していただきます。世帯の所得状況に応じて負担割合が変わりますので、忘れずに所得の申告をお願いします。
|
負担割合 |
区分 |
対象 |
|---|---|---|
|
3割 |
現役並み所得者((注意)保険外診療については、全額自己負担となります。) |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者 |
|
1割 |
一般 |
【区分1.】、【区分2.】、【現役並み所得者】以外の方 |
|
1割 |
区分2. |
世帯の全員が住民税非課税の方 |
|
1割 |
区分1. |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方 |
(注意)次のようなときには、保険証が使用できません。
- 病気とみなされないとき
健康診断・人間ドック・予防注射・歯列矯正・軽度のわきが、しみ・美容整形など - ほかの保険が使えるとき
仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります) - 給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や事故、けんかや泥酔によるけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき
申請により負担割合か3割から1割に変わる方について
次の条件を満たす場合、申請により負担割合が3割から1割になります。
|
70歳以上(65歳以上の後期高齢者医療被保険者の方を含む)の人数 |
合計収入 |
|---|---|
|
1人 |
383万円 |
|
2人以上 |
520万円 |
(注意)合計収入は、経費を差し引く前の収入での判定になります。
(注意)世帯構成の変更(転入・転居等)によっても変化する場合があります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 印かん
- 収入の分かる書類(確定申告の控え等)
医療費が高額になったとき
同じ月内の保険適用となる医療費の自己負担額が次の表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は外来(個人単位)を適用した後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
自己負担限度額について
|
区分 |
外来 |
外来+入院 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
|
区分2. |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分1. |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈)過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
区分が【区分1.】【区分2.】(住民税非課税世帯)に該当している方が医療機関を受診する際に限度額を適用してもらうには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
入院の予定があるときは事前に、役場後期高齢者医療担当窓口にて申請してください。
(注意)区分が【現役並み所得者】【一般】の方は保険証を提示することで、限度額が確認されます。
申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
入院時食事代の負担について
入院した際の食事代は、一食あたり下記の標準負担額を負担する必要があります。
区分が【区分1.】【区分2.】の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、役場後期高齢者医療担当窓口にて申請してください。
|
現役並み所得者及び一般 |
260円 |
|---|---|
|
区分2 90日までの入院 |
210円 |
|
区分2 過去12ヶ月で90日を超える入院(注釈) |
160円 |
|
区分1 |
100円 |
(注釈)過去12ヶ月に「区分2.」の減額認定証を交付されていた方が対象になります。
該当する方は役場後期高齢者医療担当窓口お問い合わせください。
高額療養費とは
入院等で月の初めから月末までの1ヶ月分の支払いの合計額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額を高額療養費といいます。
該当したときは超えた金額をお戻しいたします。広域連合から通知が届きましたら、役場後期高齢者医療担当窓口にて振込口座等の申請していただくようお願いします。また、一度申請していただくと、次回以降は口座に自動的に振込みになります。
申請に必要なもの
- 印かん
- 被保険者名義の通帳
(注意)被保険者以外の口座に支払うときは、委任欄への記載
平成24年4月1日から外来診療で自己負担限度額が適用されるようになりました
これまでは外来診療時は自己負担分を全額医療機関にお支払いいただき、払いすぎた分を後日、高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは入院診療に限らず外来診療でも上記限度額が適用されるようになりました。
このため外来診療を受ける方で、[区分1.][区分2.]に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等で提示すると、1ヶ月に一医療機関につき自己負担限度額(8,000円)を超える額を窓口で支払う必要がなくなります。
区分が[現役並み所得者][一般]の方は保険証を提示することで、限度額が確認されます。
注意
[区分1.][区分2.]の方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を出さないで受診した場合は一度[一般]の区分でお支払いいただき、後日、高額療養費でお返しいたします(但し、入院時の食事代の差額は戻りません)
厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要なとき
下記の厚生労働大臣が指定する疾病に該当する方(加入前の医療保険で「特定疾病療養受療証」の交付を受けた方)は、役場後期高齢者医療担当窓口で申請してください。医療機関での窓口負担額が1医療機関につき1万円になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障がいの一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 特定疾病に該当していることを確認できる書類(医師の診断書、障がい者手帳等)
申請をして後から受ける給付(療養費)について
医療費を全額自己負担したとき
やむを得ない理由等で保険証を提示できずに医療費をいったん全額自己負担した場合、申請により、自己負担分(1割または3割)を除いた額が支給されます。
なお、保険適用外の医療行為は対象になりません。
申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 領収書
- 診療報酬明細書
- 通帳
コルセットなどの治療用補装具を作ったとき(療養費の支給)
医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 領収書
- 医師の装具装着に関する意見書
- 通帳
はり・灸などの施術を受けたとき(療養費の支給)
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたりした時は、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 明細がわかる領収書
- 医師の同意書(医師が必要と認めた場合)
- 通帳
重病人の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
医師の指示による一時的・緊急的な必要性があり、重病人の入院、転院などで移送の費用がかかったときは、申請により広域連合の承認が得られた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。
申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 領収書
- 医師の診断書または意見書
- 通帳
(注意)上記は申請の後に、福島県後期高齢者医療広域連合から「口座振込」によるお支払となります。
(注意)口座確認のため、申請には通帳をお持ちください。
死亡したとき
加入者が死亡したときは、申請により葬儀を行った人に対して葬祭費(5万円)が支給されます。
申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 葬祭執行者(相続人)の通帳
(注意)上記は福島県後期高齢者医療広域連合から「口座振込」によるお支払となります。
(注意)申請の際「申立・誓約書」の届出をすれば、その他の給付があった場合、受け取ることができます。
(注意)葬祭を行った日から起算して2年を経過してしまうと時効によりお支払いができなくなります。
交通事故などにあったときは
交通事故など「第三者の行為」によって、ケガや病気をしたときは届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
医療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、福島県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、あとで加害者に請求をすることになります。
(注意)医療を受けられる際には、傷病を受けた原因(交通事故等)を必ず医師に話しましょう。
(注意)事故にあったときは、必ず警察署に届け出て、加害者の「氏名」「住所」「連絡先」を聞き、メモを取りましょう。
申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 事故証明書(後日でも可)
健康管理について
後期高齢者健康診査
生活習慣病の早期発見・治療のため、町では毎年4月下旬から6月上旬にかけて、後期高齢者が無料で受けられる集団健診を実施しています。
あわせて、若干の費用負担はありますが、町が実施している各種がん検診も受けていただくことができます。
健診等を受けて、ご自身の健康管理に役立ててみてはいかがでしょうか。
後期高齢者医療制度の申請に必要なもの
|
こんなとき |
申請に必要なもの |
|---|---|
|
75歳になったとき |
手続きは不要です |
|
65歳以上の方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度へ加入したいとき |
|
|
県外から転入したとき |
|
|
県内の市町村で転居したとき |
|
|
保険証をなくした(破いた)とき |
|
|
死亡のとき |
|
|
申請で自己負担限度額が3割から1割に変わるための通知が届いたとき |
|
|
入院の予定があるとき |
|
|
厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要なとき |
|
|
保険料の納付書をなくしたとき |
役場担当窓口にお電話ください。 |
|
保険料の納付証明書が欲しい |
役場担当窓口に申し出てください。
|
|
災害等で保険料を納めるのが困難なとき |
|
|
福島県広域連合から高額療養費の通知が届いたとき |
|
|
交通事故にあったとき |
|
|
コルセットなど治療用装具を作って代金を支払ったとき |
|
詳しくは後期高齢者医療担当窓口まで
後期高齢者医療制度の申請書等について
後期高齢者医療制度の申請書等については福島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度担当窓口
本庁住民生活課国保年金係 0241-62-6120
舘岩総合支所町民課住民係 0241-78-3325
伊南総合支所町民課住民係 0241-76-7712
南郷総合支所町民課住民係 0241-72-2225








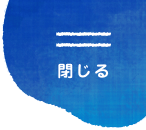


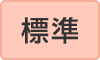


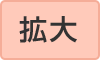



更新日:2021年04月01日